
<国内最大級の産業廃棄物の不法投棄により、「ごみの島」と呼ばれた瀬戸内海の離島・豊島(てしま)=香川県土庄(とのしょう)町=で、20年余りに及んだ処理事業が終了し、県が30日、現地を公開した。>
これは今年3月31日の毎日新聞朝刊に「香川・豊島 ごみの山消えても残る地下水汚染 産廃処理事業終了」という見出しで掲載された記事の冒頭部分です。豊島は四国・高松港の北約12kmの瀬戸内海に浮かぶ島で、四方を島に囲まれた多島海美の中にあります。1970年代後期からこの島に有害産業廃棄物が大量に投棄されるようになり、住民に健康被害が出るようになりました。島の住民は激しい撤去運動を繰り広げ、2003年に成立した産廃特措法に基づいて2019年7月までに総計約91万3,000トンの廃棄物と汚染土が豊島の西約4㎞にある直島に運ばれ、香川県が建設した「直島環境センター中間処理施設」で焼却・溶融化処理されました。そして今回、汚染地下水を浄化する高度排水処理施設の整備や整地作業が終わり、「わが国初の汚染地修復の国家的取り組み」と言われた処理事業が完了したと報道されたのです。
ちなみに、廃棄物と汚染土の総量は毎年処理対象量の見直しがあり、2012年7月には最大の93万8,000トンが見込まれましたが、2017年に搬出がいったん完了したあとに発見された産廃・汚泥を含めて最終的な量は処理約91万3,000トンとされています。
「豊島事件」とも称されるこの産廃不法投棄問題は、島の西部の土砂を大量採取した土地22haに業者(豊島観光)が1978年から有害産業廃棄物を不法に投棄し始めたことに始まります。島の住民は反対運動や裁判を起こしましたが、業者は「みみず養殖」を行うとして香川県知事の許可を取り、認められるとすぐに無許可の産業廃棄物を持ち込んだのです。輸送船で島外から自動車の破砕ごみや廃油などの有害産廃を運び込み、それを満載したダンプカーが島内を走り回り、野焼きの黒煙が立ち上りました。住民の間に咳が止まらない健康被害が発生し、ぜんそくのような症状を持つ生徒・児童は全国平均の10倍にのぼったそうです。
1990年11月、兵庫県警が「ミミズの養殖を騙った産廃の不法投棄」の容疑で業者を摘発、強制捜査をしたことにより産廃搬入は止まりました。しかし、膨大な量の有害産廃が残り、有害物質を含む水は海に流れ続けました。事件報道によるイメージダウンによって豊島産の産物販売や観光業も壊滅的な打撃を受けました。そこで島の住民は「廃棄物対策豊島住民会議」を結成し(再発足)、廃棄物撤去を求める運動を展開しました。1993年11月に香川県と業者、排出事業者などを相手取った公害調停を国に申請し、長い“草の根の闘い”を経て2000年6月6日、やっと知事の謝罪と原状回復の合意を勝ち取ったのです。
廃棄物と汚染土の搬出、直島での中間処理が終わり、昨年7月に専門家の検討会が全9区域・区画で地下水が「排水基準」をクリアしたと認定しました。今年3月には整地作業が終わり、予定されたすべての作業の完了が専門家会議で確認されたのです。しかし、問題がすべて解決したわけではありません。地下水が自然浄化によって「環境基準」以下になれば県が住民に土地を引き渡しますが、その達成時期がいつになるかわかりません。
住民の島を挙げてのゴミ問題との闘いは法律や国の政策を変えました。島内にはごみ問題と運動の歴史を学ぶ「豊島のこころ資料館」があり、住民によって運営されています。
図:豊島の産廃問題を巡る経緯(毎日新聞2023年3月31日記事より)




















 船津屋の板壁が一部くりぬかれて、高さ1メートルほどの石碑(右)が建てられている。そばに「歌行燈句碑」と題する説明板。
船津屋の板壁が一部くりぬかれて、高さ1メートルほどの石碑(右)が建てられている。そばに「歌行燈句碑」と題する説明板。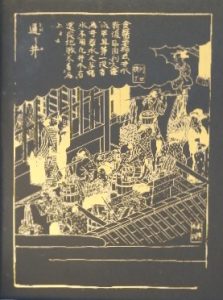

 桑名藩には越後に飛び地があった。その領地は5万石の石高があり、柏崎に陣屋(役所)が置かれていた。役職が横目という藩の下級武士・渡部勝之助が柏崎陣屋の勘定人を命じられたのは天保10(1839)年の正月、36歳のときだった。下っ端役人ながら「学問ができ仕事もできる」と高く評価されていた勝之助にとって、このお役替えは出世ではあった。
桑名藩には越後に飛び地があった。その領地は5万石の石高があり、柏崎に陣屋(役所)が置かれていた。役職が横目という藩の下級武士・渡部勝之助が柏崎陣屋の勘定人を命じられたのは天保10(1839)年の正月、36歳のときだった。下っ端役人ながら「学問ができ仕事もできる」と高く評価されていた勝之助にとって、このお役替えは出世ではあった。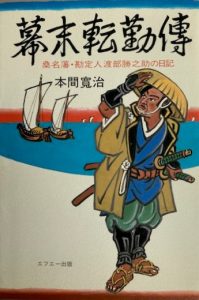 桑名は長良川と合流する揖斐川に面しており、伊勢湾にそそぐ河口近くに位置する。「七里の渡し(写真)」は桑名から熱田神宮がある宮宿まで、距離が7里であることからつけられた。勝之助は30キロ近い伊勢湾の船旅の道中、来し方行く末がさまざまに去来したのであろう。柏崎まで旅日記をつけた。柏崎に着いた後もまめに日記をつけ、平太夫に送った。平太夫からも日記が勝之助のもとに送られ、交換日記の形になった。この日記を基に新聞記者の本間寛治さんが1988年、『幕末転勤傳――桑名藩・勘定人渡部勝之助の日記』(エフェー出版)(写真左)を著した。
桑名は長良川と合流する揖斐川に面しており、伊勢湾にそそぐ河口近くに位置する。「七里の渡し(写真)」は桑名から熱田神宮がある宮宿まで、距離が7里であることからつけられた。勝之助は30キロ近い伊勢湾の船旅の道中、来し方行く末がさまざまに去来したのであろう。柏崎まで旅日記をつけた。柏崎に着いた後もまめに日記をつけ、平太夫に送った。平太夫からも日記が勝之助のもとに送られ、交換日記の形になった。この日記を基に新聞記者の本間寛治さんが1988年、『幕末転勤傳――桑名藩・勘定人渡部勝之助の日記』(エフェー出版)(写真左)を著した。

と奄美三線のバチ-300x225.jpg)

