手作り映画館 写真ギャラリー

LAPIZ ONLINEは609studioに統合しました。
www.609studio.com
手作り映画館 写真ギャラリー
戦争の惨禍を映す

2020年からのコロナ感染拡大で元町映画館が苦境に陥るなか、私は『ドンバス』(セルゲイ・ロズニツァ監督)を見たのだ。
ウクライナ東部のドンバスは親ロシア派勢力の強いところで、2014年、一方的にウクライナからの独立を宣言。ウクライナ軍との武力衝突が日常化し、事実上内戦状態になっていた。映画はウクライナ内部の深い分断の溝による悲劇をダークユーモアを交えてえがき出したものだが、私が注目したのは政府側のアゾフ大隊の所業だった。隊の中にネオナチ的な兵がいて、親ロシア派の住民に暴行する場面もある。プーチン大統領が、ウクライナにはネオナチがいると、戦争の口実にしたことを思い起こし、戦争のためには、敵の弱みを最大限利用してプロパガンダにするものと知ったのであった。
同館で私が見た2回目の映画は『島守の塔』(五十嵐匠監督)。2022年8月だった。映画は沖縄戦最中の沖縄県知事、島田叡(あきら)の苦悩に迫った。高校、大学時代、野球の名選手だった島田は東大を出たあと内務省に入省。敗色が濃い1945年1月、米軍の上陸が必至とみられる沖縄県の知事を任命された。家族を残して沖縄に赴任した島田は県民の食糧確保に奔走。米軍が上陸し、摩文仁の丘に追い詰められて死を決した部下に「命どぅ宝、生き抜け」と諭して逃がす。自らは壕にとどまり消息は不明に。遺体は発見されていない。
今は県営平和祈念公園になっている摩文仁の丘から見た沖縄の青い海を思い浮かべながら、涙してこの映画を見たのであった。
採算度外視の映画

政府は今年3月、コロナ対策を緩和し、マスクの着用を個人の意思に委ねた。そんな中の4月下旬、私は元町映画館で『浦安魚市場のこと』(歌川達人監督)を見た。冒頭に述べた魚市場が舞台の映画である。
浦安魚市場は1953年、千葉県浦安市に設置された。30店舗が入居、漁師が浦安で水揚げした魚介類をはじめ、築地市場で仕入れた鮮魚が販売された。元来、浦安の海は漁場だったが、経済成長とともに埋めたてが進み、臨海工場地帯になる一方で、東京ディズニーランドの開設によって、漁港の町ではなくなった。住民の買いもの動向も大きく変わり、消費者の80%以上は魚介類をスーパーで買うようになった。
加えて市場の2階建てビルが老朽化し、耐震構造になっていないこともあり、2019年3月31日、閉鎖され、65年の歴史の幕を閉じた。
私は閉鎖される少し前に同市場をたずねた。ほとんどの商品は売り切れていた。着いたのがすでに午前11時を過ぎていたこともあるが、閉鎖が決まって商品を余らせないようにしていたこともあるのだろう。売り物のない店には寂しさが漂っていて、いつもは威勢がいいであろう店員たちも、ほとんど言葉を交わさず、物静かな市場であった。
映画は「泉銀」という店の、40代半ばの店主を主人公にして描かれた。店主は「市場に客を呼び込もう」と市場の近くの路上でロックのライブを開き、自らボーカルをつとめるなど、苦心に苦心を重ねる様子を克明に描写。3人の子どもには南房総の漁港でクジラをさばく様子を見せたり、築地市場に連れて行ったりと、鮮魚商の内側を教える。
市場閉鎖の直前、泉銀の店主は復興したばかりの岩手県宮古市の市場に招かれ、マグロをさばく。たまたま私はこのころに宮古市を訪ねているだけに、このシーンに胸が詰まった。新たに生まれ変わる三陸の魚市場と、姿を消す大都会の市場。市場経済は非情である。
神戸の人たちのなかに浦安魚市場に関心がある人はまずいないだろう。実際、私を入れても入館者は7、8人。人件費も出ないだろう。それにもかかわらず上映を決断した元町映画館のスタッフに私は敬意を表したい。世の中、経済の論理だけで動くわけではないのだ。
映画館の天井が低くとも、映写機の位置が低くとも、そして待合スペースがなくてもいいではないか。儲からない映画も上映する。その気概に私は拍手喝采である。
ここまで書いて、小学校のころ、学校の講堂で映画が上映されたのを思い出した。美空ひばりが双子の姉妹として登場する映画だった。スクリーンに児童の影が映ったが、気にはならなかった。あるいは私が映画が好きになった原点だったのかもしれない。ふと思う。元町映画館はあるいは新たな映画文化を切り開くきっかけになるかもしれない。手作り映画館が地元の映画好きを掘り起こすことになるのではないか。手作りのミニ映画館が地域文化の担い手になってくれることを私は願っている。(明日に続く)

神戸一の繁華街・元町商店街の一角に「元町映画館」ができたのは13年前の8月。以来、「知る人ぞ知る」といったかんじで、ひっそりと営業をつづけてきた。同映画館はいわゆるミニシアターの一つであるが、他の小映画館と決定的に異なるのは、映画館らしくない映画館。いうならば手作り映画館なのである。はじめてこの映画館に入ったとき、天井が低いのに驚いた覚えがある。以来、私は元町映画館のファンになった。4月末、神戸の人がまず見ないであろう映画が上映された。舞台は私が訪ねたことがある千葉県の魚市場。案の定、客は10人足らず。採算よりもいい映画を。映画館主のそんな心意気がたまらない。
パチンコ店からの変身
私が同館で見た最初の映画は『ドンバス』であった。ウクライナ戦争が始まって3カ月半ほどたった2022年6月、新聞で上映を知った。ネットで前売り券を買い求めようと同館のホームページを開いたところ、当日、窓口でしか販売していなかった。上映の40分前に同館を訪ねてチケットを購入。この際整理券を渡され、上映の10分前に来るように、と言われた。
指示通り、10分前に行ってわかった。館内には待合室がなく、外で待つしかない。外は商店街である。早くから街路で待たれると、隣近所の商店に迷惑をかけるのだ。
館内に入って驚いたのは冒頭に述べたように天井が低いこと。高さは2・5メートルくらい。背の高い人なら天井に手が届きそうである。予告編が始まると、客席の後ろを横切った人の影がスクリーンに映った。後ろを振り返った。映写機の位置が低い(高さ1・5メートルくらい)ので、その前を通ると、影が映るのだ。係員が「上映中、トイレに行かれる方は腰をかがめてお通りください」と注意していた。
私はミニシアターが好きだ。大阪・十三の「第七芸術劇場」、西九条の「シネ・ヌーブォ」、宝塚の「シネピピア」などで何度も映画を見た。いずれも100席にも満たない映画館だが、戦争や原発、環境などがテーマの地味な名画が上映される。これらの映画館は小さいけれども映画館としてつくられており、客が立とうが動こうが、それで映写の邪魔になる(他の客に迷惑をかけるとしても)ことはない。客の影が映るというのは、元町映画館がもともと映画館としてつくられたのでないからではないのだろうか。
映画が終わり、外に出るとさっそくネットで調べた。「2000年、小児科医の堀忠は元町4丁目商店街の閉店したパチンコ屋を購入し、映画館開館の準備を進めた」とある。元はパチンコ店だったのだ。パチンコをするのに天井がそれほど高い必要はあるまい。パチンコ店が映画館になった例はおそらくほかにはないだろう。
映画好きの小児科医師

堀忠とはどういう人物なのだろう。2020年に元町映画館が開館して10年がたったのを記念して刊行された『元町映画館ものがらり――人、街と歩んだ10年、そして未来へ』(神戸新聞総合出版センター)をひもといた。書き出しは堀さんの紹介である。
堀さんは子どものころ、元海軍軍医の父親によく映画館に連れられた。高校生になると文化祭で16ミリフイルムの上映会を催すほどの映画好きになった。医師になって後の1990年代前半、40歳くらいのころ、映画館をもちたくなった。ミニシアターがない神戸にターゲットをしぼって映画館にできそうな建物を探しまわり、1999年、元町商店街にある2階建てのテナントビル「元町館」を手に入れた。ここにパチンコ店が入っていたのだ。
2005年、堀さんら映画好きグループが中心になって「シネマをつくろう!」というプロジェクトがスタート。2006年、主要メンバーが元町館に集まって映画館づくりのための経費見積もりを行った。資金のメドは立たなかったが、堀さんが同僚から100万円を借りるなどして資金を工面、2010年4月、着工にこぎつけた。
工事に合わせて、映画館ができるまでをドキュメンタリー映画に収めることにした(映画は『街に・映画館を・造る』=木村卓司監督。2011年4月、同館で公開)ところが、映画好きならではの着想だ。2010年7月に工事が完成。上映場は幅約8メートル、長さ約18メートル、66席。元パチンコ場としては堂々たる出来栄えといえるだろう。
オープンは2010年8月21日。オープニング作品はグォ・ヨウ、スー・チー主演の中国映画『狂った恋の落とし方。』と高畑勲監督の『赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道』。オープン初日、不倫に苦しむ女性と一夜にして富豪になった中年男女の恋愛を描いた『狂った恋の落とし方。』は北海が舞台となったことも手伝って76人が入場。『赤毛のアン』にも47人が入り、上々の滑り出しになった。
その後、『勝手にしやがれ』などで知られるヌーベルバーグの旗手、フランスのゴダール監督の作品や富野由悠季節監督の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』など、多方面のジャンルの映画を意欲的に上映。戦後の激動の台湾を描いた『悲情城市』(1989年、侯孝賢監督)は2013年に上映された。私はこの映画の舞台となった台湾の現地をたずねたことがある。上映はその1年前だ。見ていれば現地でいっそうの興趣をおぼえたであろう。(明日に続く)

「核のゴミ処分の国際ルールを」
東京新聞の記者たちとの討論では使用済み核燃料の処分についても話題にのぼった。わが国の原発の半数以上が、使用済み核燃料の貯蔵率について、法令で定められた量の8割を超えており、「トイレなきマンション」が現実問題になっている。六ケ所村の再処理工場建設は迷走をつづけ、プルサーマル計画は、高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉で頓挫している。こうしたなか、高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)の最終処分場の選定をめぐり、北海道の寿都、神恵内の2町が公募に応じた。
この討論は2町が手を挙げる前に行われたが、処分についての見通しがほとんどないことはその後も変わらない。
ファンに反原発を刻み込む

坂本さんは2007年、『ロッカショ 2万4000年後の地球へのメッセージ』(講談社)を著した。サブタイトルの「2万4000年」は再処理して取り出すプルトニウムの半減期だ。坂本さんは同書の冒頭、「まず知るということが大切。知らないということ、無知ということは、死を意味するというか、死につながる」と記した。そして「長期にわたり管理が必要な核物質をなぜ利用する必要があるのか。再処理工場が稼働した場合、環境への影響はどうなるのか
――などと疑問を投げかけた。(4月11日、毎日新聞夕刊)
坂本さんの著書に対し、元東電副社長や元東芝原子力事業部長らで組織する「エネルギー戦略研究会」有志が08年、出版元の講談社に「国民に再処理工場反対を呼びかけようとするセンセーショナルな出版物」などと抗議した。しかし、日本電燃が提出した申請書類約6万ページのうち3100ページに記載漏れなどの不備があり、原子力規制委員会が今年4月、同社社長に「信用に関わる問題」と厳しく指摘したことにみられる現状では、坂本さんが再処理工場に不安を持つのは当然であろう。
坂本さんは福島第一原発の事故後の2011月8月15日、福島市で開かれた芸術の祭典「FUKUSHIMA!」に参加。同市在住の詩人、和合亮一さんがツイッターで発表した詩を朗読する中、約1000人の聴衆を前に即興でピアノを弾いた。
さらに「一刻も早い脱原発」を訴えてロック・フェスティバル「NO MUKES」(ノー・ニュークス)を始めた。坂本さんの呼びかけに賛同したアーティスト、市民団体、メディアが参加して2012年に幕張メッセで第1回のフェスティバルが行われ、YMOをはじめ、トップアーティストが熱演をふるった。2014年の第2回イベントには坂本は咽頭がんの治療のため参加できなかったが、2015年イベントにはトークセッションに出演。17年、19年イベントにも顔を見せ、坂本ファンは「反原発」の意義を深く刻み込んだ。
「事故後も根強い原発神話」
東京新聞記者たちとの討議のなかで、坂本さんは「電力は原発でしかまかなえないと思っている人はまだまだ多く、原発がなくなったら停電になるとか、入院している人が死亡するとか言っている」と日本人の保守性を指摘。「電力=原発という神話は、これだけの事故の後でさえ根強い。チェルノブイリと同じ、人類最悪の事故が起きて、少しは社会が変わるかと期待したけれど、意外と手強い。むしろ前より悪くなりつつある」と悲観的な発言をした。
と言いつつも、坂本さんは「3・11によって、問題の所存に気づいた人はものすごく多い。そこは希望だと思う」と語った。話は国会前で行われた「反原発デモ」にうつり、デミ参加者が減少していることに言及。「関心があってもデモに来ないひとも多い。事故後、社会に声を上げず、関東から逃げだした人も多い。非常に強い関心を持っていても、必ずしも社会的に声を発しない人はたくさんいる」と、″声なき反原発の声″に期待をにじませた。
東京新聞記者から「(脱原発運動を進めるうえで)どういう未来を提示できるかだ。そのあたりはどう考えるか」と質問されたのに対し、「自分たちは(原発リスクを)言ってるつもりだが、届いてない現実がある」としたうえで「リスクばかり、悪い面ばかり言うと人間は暗くなるから、良いビジョンを示すことも大切。そのためには今どうすればいいか。ありうべき未来に向かって、そこから逆に今の行動を決める。バック・キャスティングという考え方をしたらいい」と提言した。(明日に続く)

――東京新聞記者との討議から――
今年3月28日に亡くなった作曲家・坂本龍一さんが脱原発運動に熱心に取り組んでいたことを新聞報道で知った。映画『ラストエンペラー』の音楽に携わり、米アカデミー賞作曲賞を受賞するなど、世界的な作曲家として名を成した坂本さんだが、福島原発事故の以前から、青森県六ケ所村で進められている使用済み核燃料再処理工場について、「死につながる」と警告を発していたというのだ。福島事故から2年9カ月後の2013年12月、坂本さんは東京新聞の本社で同社記者たちと原発問題について討議した。その白熱ぶりがレポートにまとめられ、『坂本龍一×東京新聞 脱原発とメディアを考える』(東京新聞編集局編)と題して刊行された。同書を中心に、天才的作曲家の原発観をみてみたい。 “原発を考える《坂本龍一の「脱原発」#1》文 井上脩身” の続きを読む

新聞業界はいま危機を迎えています。スマホの普及にともない、中・高年層までが新聞をとらなくなったのです。そんななか、東日本大震災の被災地で一人の女性が新聞の発行を始め、「知りたい情報が載っている」と避難者らから信頼されたと知りました。女性は、取材から編集、広告取りまで1人でやり抜いたそうです。ネットなどを通じてさまざまな情報を知ることができる便利な世の中になりましたが、暮らしに必要な身の回りの情報を得るのはそうたやすいことではありません。大手新聞、タウン紙、広報紙のいずれでもない「ひとり新聞」。その身軽さのゆえに読者のニーズに応えることができたのだと思います。 “2023夏号Vol.46《巻頭言》Lapiz編集長 井上脩身” の続きを読む
俳句になった元本陣のカワウソ

一の鳥居のすぐそばの東海道沿いに「しちりのわたし」と刻まれた石碑が建っている。この石碑の脇では、鉄筋三階建てのビルが修理工事中だ。その壁に「山月」のネオン。料理旅館「山月」である。脇本陣「駿河屋」の一部がこの料理旅館に残っているという。「山月」の左隣は木造二階建ての瀟洒な料理旅館。入り口に「船津屋」と書かれた照明灯がたっている。その名の通り、裏庭から直接船に乗ることができた。ここが元の大塚本陣である。
 船津屋の板壁が一部くりぬかれて、高さ1メートルほどの石碑(右)が建てられている。そばに「歌行燈句碑」と題する説明板。
船津屋の板壁が一部くりぬかれて、高さ1メートルほどの石碑(右)が建てられている。そばに「歌行燈句碑」と題する説明板。
句は「かはをそに火をぬすまれてあけやすき 万」。劇作家、久保田万太郎が詠んだ句だ。
説明板は明治の文豪・泉鏡花(1873~1930)が明治42(1900)年、講演のため来桑、ここ船津屋に宿泊した。この時の印象を基に小説『歌行燈』を書き、翌年1月号の『新小説』に発表した」としたためられている。久保田万太郎は1939年、戯曲『歌行燈』を書くために船津屋に逗留、旅館の主人の求めに応じて句をつくった。この句に出てくる「かはをそ」はカワウソのこと。泉鏡花の小説に現れるという。どういうことだろう。帰ってから『歌行燈』を読んだ。
小説は次のような一文から始まる。
宮重大根のふとくして立てし宮柱は、ふろふきの熱田の神のみそなわす、七里のわたし浪ゆたかにして、来往の渡船難なく桑名につきたる悦びのあまり……
これは十辺舎一九の『東海道中膝栗毛』の五編上「桑名より四日市へ」の書き出しと全く同じ。『東海道中膝栗毛』はこの後「めいぶつの焼蛤に酒くみかはして、かの弥次郎兵衛喜多八なるもの、やがて爰(ここ)を立出(たちいで)たどり行くほどに」とつづく。『歌行燈』も主人公、源三郎が弥次郎兵衛になった気みなって、湊屋(モデルはいうまでもなく船津屋)で芸の出来ない仲居と軽妙な会話を楽しむという筋立て。その湊屋について、うどん屋の女房が主人公に次のように話す。(筆者註・口語に書き換えている)。
z奥座敷の手すりの外が海といっしょの揖斐の川口じゃ。白帆の船も通ります。スズキがはねる。ボラは飛ぶ。他に類のない趣のある家じゃ。ところが時々崖裏の石垣からカワウソが入りこんで、板廊下や厠についた灯りを消していたずらするといいます。
辞書で調べると、カワウソの和名は「カワオソ」。「川に住む恐ろしい動物」の意味があるといわれ、加賀では城の堀に住むカワウソが女に化けて、男を食い殺したという言い伝えがあるという。
船津屋は江戸時代、本陣であった。大名が泊まる格式高い宿所にカワウソが化けてでたとは考えがたいが、加賀の例のように、桑名城の堀にカワウソがすんでいて、悪さをすることがあったのかもしれない。
暮らしを守る通り井の水
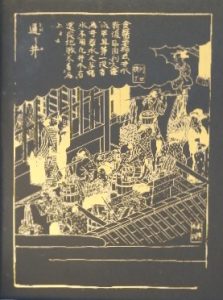
「七里の渡し」から旧東海道を歩いた。両側に料亭などが立ちならび、「焼きハマグリの街」ならではの、思わずつばが出そうな雰囲気を醸している。その街道の両端に幅約50センチの細長い石製板が帯状にしかれている。他の宿場町では見られない道路模様だ。何だろう。
途中、その説明がかかれた標識がたっていて、疑問が解けた。
桑名では地下水に海水が混じるため、寛永3(1626)年、町内の主要道路の地下に筒をうめ、町屋川から水を引いて水道をつくった。これを「通り井」といい、道路の中央に方形の井を設けて一般の人々が利用できるようにした。1962年、道路工事のさい、「通り井」の一つが発見されたという。
勝之助は柏崎の街について「御国(桑名のこと)と違い、役所仕舞いにてもそば売りも参らず、勿論酒も無し」と嘆いている。ということは桑名では、仕事が終わるころを見はからってそば売りがやってきたのだろう。そばをゆで、つゆを作るには当然水がいる。そば売りは通り井から水をくんだに相違ない。できることなら私もそばを食べたいものだ。堀端を歩きたくなった。
桑名城本丸周辺は石垣が残っているにすぎず、いささか殺伐とした光景である。旧東海道に戻ってそぞろ歩いていると、建て込んだ街並みの中に鳥居が見えた。桑名宗社と呼ばれる春日神社の鳥居だ。青銅製である。東海道を行く人たちはこの神社で旅の安全を祈願したにちがいない。神社の本殿では赤ちゃんを抱いた夫婦が神職のお祓いを受けていた。勝之助も出立前、生まれて間もない娘のために妻と共にお祓いを受けたかもしれない。
この後しばらく辺りをめぐって、宿場町の痕跡を探したが、美濃への出入り口としての番所が置かれていたという「三崎見附跡」以外に撮影ポイントがないようなので、メーンの通りを桑名駅に向かった。途中、海蔵寺という寺の前を通りかかると「薩摩義士墓所」ののぼりが門前にかかっていた。中に入った。境内の奥に、23基の墓がコの字型にならんでいる。説明板によると、宝暦4(1754)年、薩摩藩は幕府から木曽三川の分流工事を命じられ、947人を送り出した。工事は河口から50~60キロの範囲内、200カ所以上にのぼった。40万両(約320億円)もかかった大治水工事は1年で完了したが、幕府への抗議のための自害や病気などで84人が命を落とした。うち23人が義士としてまつられたという。
この工事によって、桑名は城下町として、また宿場町として、安心して暮らせる街になったのはまぎれもない。だが、幕府の命令は薩摩藩にとって非情であった。1200キロも離れた木曽三川のために莫大な資金を藩で用意しなければならないのだ。23義士の家族や親族の末裔は、やがて戊辰戦争で官軍の兵として幕府軍と戦っただろう。幕府方の桑名藩は朝敵となり、薩長の官軍に降伏した。何かの因縁であろうか。
ところで勝之助である。元治元(1864)年、再び桑名の土を踏むことなく柏崎で死んだ。63歳だった。戊辰戦争の4年前であった。
勝之助はどれほどか七里の渡しの船で桑名に帰る夢を見たことであろう。勝之助の心中をおもいつつ、私は桑名から名古屋に向かう電車にのった。
水道完備の七里の渡し

サラリーマンにとって転勤は世のならい。私は7、8回転勤した。江戸時代、城勤めの侍も江戸詰めなどの転勤はあったが、地方への転勤で一家が引き裂かれた例があると最近知った。桑名藩士の渡部勝之助が越後・柏崎への異動を命じられ、長男を残して妻と任地におもむいたというのだ。勝之助は桑名の「七里の渡し」で引越しの旅に出た。渡しがあるということは、湊の前の宿場はにぎわっていたにちがいない。東海道の桑名宿を訪ねた。
柏崎陣地への転勤命令
 桑名藩には越後に飛び地があった。その領地は5万石の石高があり、柏崎に陣屋(役所)が置かれていた。役職が横目という藩の下級武士・渡部勝之助が柏崎陣屋の勘定人を命じられたのは天保10(1839)年の正月、36歳のときだった。下っ端役人ながら「学問ができ仕事もできる」と高く評価されていた勝之助にとって、このお役替えは出世ではあった。
桑名藩には越後に飛び地があった。その領地は5万石の石高があり、柏崎に陣屋(役所)が置かれていた。役職が横目という藩の下級武士・渡部勝之助が柏崎陣屋の勘定人を命じられたのは天保10(1839)年の正月、36歳のときだった。下っ端役人ながら「学問ができ仕事もできる」と高く評価されていた勝之助にとって、このお役替えは出世ではあった。
だが、単純に喜べない事情があった。勝之助の家族は妻おきく(24歳)と数えで4歳の長男鐐之助だけだが、おきくはおなかに子どもを抱えていた。勝之助は迷った末、鐐之助を叔父の渡部平太夫に預けることにした。現在の会社の命による転勤でもよくあるが、いったん勝之助だけが単身で赴任。2カ月後の5月、桑名に帰省した。おきくは娘おろくを産んだばかりだった。このころ、江戸では渡辺崋山や高野長英らが幕府に捕らわれる「蛮社の獄」が起きていた。しかし、桑名城下の組長屋に暮らす勝之助には無縁の世界であった。
5月30日六つ半(午前7時)、勝之助一家は柏崎に出立。勝之助夫婦は寝ていた鐐之助を起こさず長屋をでた。勝之助はそのとき、いずれ桑名に戻ると一緒に暮らせる、と思った。平太夫やおきくの実家の人たち、勝之助の友人らが「七里の渡し」まで見送ってくれた。
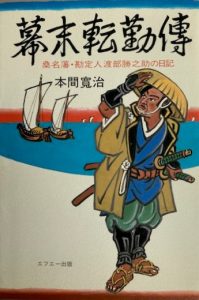 桑名は長良川と合流する揖斐川に面しており、伊勢湾にそそぐ河口近くに位置する。「七里の渡し(写真)」は桑名から熱田神宮がある宮宿まで、距離が7里であることからつけられた。勝之助は30キロ近い伊勢湾の船旅の道中、来し方行く末がさまざまに去来したのであろう。柏崎まで旅日記をつけた。柏崎に着いた後もまめに日記をつけ、平太夫に送った。平太夫からも日記が勝之助のもとに送られ、交換日記の形になった。この日記を基に新聞記者の本間寛治さんが1988年、『幕末転勤傳――桑名藩・勘定人渡部勝之助の日記』(エフェー出版)(写真左)を著した。
桑名は長良川と合流する揖斐川に面しており、伊勢湾にそそぐ河口近くに位置する。「七里の渡し(写真)」は桑名から熱田神宮がある宮宿まで、距離が7里であることからつけられた。勝之助は30キロ近い伊勢湾の船旅の道中、来し方行く末がさまざまに去来したのであろう。柏崎まで旅日記をつけた。柏崎に着いた後もまめに日記をつけ、平太夫に送った。平太夫からも日記が勝之助のもとに送られ、交換日記の形になった。この日記を基に新聞記者の本間寛治さんが1988年、『幕末転勤傳――桑名藩・勘定人渡部勝之助の日記』(エフェー出版)(写真左)を著した。
本間さんは同書のなかで勝之助らの「七里の渡」しでの船出を以下のように表している。
木曽三川の一つ、揖斐川河口にひらけた七里の渡しの朝は活気があふれていた。水上には何艘もの帆船が沖がかりをし、川につき出た桑名の白壁が朝日に映えた。川面を渡る風はさすがに涼しく、勝之助らを乗せた帆船は滑るように伊勢湾に出た。勝之助は熱田の宮の渡しまで水路を行き、そこから陸路越後を目指した。
このくだりを読んで、私はネットを開いた。渡しの近くに本陣や脇本陣、それに桑名城があったという。宿場と渡し、それに城下が一体となっており、いわば三位一体の街のようなのだ。興味をひかれ、1月下旬、桑名に向かった。
渡しに面して建つ鳥居と櫓


近鉄桑名駅で降りると、まっすぐ「七里の渡し跡」に向かった。東に歩くこと約30分。揖斐川沿いにだだっ三之丸公園が広がっている。その名の通り、桑名城の三之丸跡にあたり、二層の櫓が建っている。「蟠龍櫓」と名づけられている。説明板によると元禄時代の火災後に再建された61の櫓のなかで、「七里の渡し」に面して建てられた蟠龍櫓は、東海道を行き交う人々が必ず目にする桑名のシンボル。歌川広重の「東海道五十三次之内桑名・七里渡口」では桑名の名城ぶりを表すため、この櫓が象徴的に描かれているという。
スマホで広重の浮世絵を見た。目の前の櫓はおとなしい造りだが、浮世絵の櫓はどこか勇壮な気迫が漂う。現在の櫓は2003年、水門の管理棟として、元の櫓を復元して建てられた。勝之助は旅立ちの際、蟠龍櫓を見たはずだ。勝之助の目におとなしく映ったか、それとも勇壮に見えたか。家族をつれてはるばる越後まで長旅をしなければならない勝之助の胸中は複雑であっただろう。
蟠龍櫓の約50メートル先に鳥居が建っている。伊勢国の一の鳥居として天明年間(1781~1789年)に建てられた。高さ約10メートルの黒っぽいこの鳥居の間に松の木が植わっていて、その緑が冬の空に映えている。鳥居の約30メートル先は揖斐川の岸辺。木の柵が設けられていて、そこに川に降りる石段がつくられている。石段をおりたところに渡しの乗り場があったのだろう。残念ながら、鉄の鎖が張られていて、今はおりられない。
そばに「七里の渡し跡」の説明板。「七里の渡しの西側には舟番所、高札場、脇本陣・駿河屋、大塚本陣が、南側には船会所、人馬問屋や丹羽本陣があり、東海道を行き交う人々で賑わい、桑名宿の中心として栄えた」とある。
現在は渡しの乗り場のすぐ前に高さ10メートル近いコンクリート壁がめぐらされ、幅約10メートルのすき間が申し訳程度につくられているだけ。そのすきまから向こう岸をのぞくしかない。伊勢湾台風で大きな被害にあったことから、沿岸の人々を守るために築かれたのであろう。やむを得ないことではあるが、はるかに宮宿の渡しの船着き場まで遠望できれば、という期待がピシャッと断ち切られ、いささかもの足りないおもいであった。
この渡し場から鳥居に戻る途中、外堀が揖斐川に平行してつくられていることに気づいた。桑名城は川を巧みに利用した水城なのだ。堀の水面に蟠龍櫓の白亜の壁が映っている。「川につき出た桑名の白壁」という、『幕末転勤傳』での本間さんの表現。なるほど、である。(明日に続く)
神社前の狭い広場で激突?


1月末、私は吹田事件の現場を訪ねた。すでに述べたように、阪大グラウンドでの集会の後、デモ隊は二手にわかれている。人民電車部隊コースをとった一団は阪急石橋(現石橋阪大前)駅に向かい、上りホームで気勢をあげ、人民電車の発車を要求、臨時電車で大阪方面に向かったという。
その現場である石橋阪大前駅上りホーム。私が自宅から大阪に行く際に利用する阪急電車はこの駅を通る。同駅から阪大に通じる商店街にある鍼灸院に何度か通ったことがあり、この駅は知り尽くしている。上りホームは箕面線ホームとの分岐点にもなっていて、そこに改札口が設けられている。改札口辺りは事件のとき、現在と同様、比較的広いスペースがあったであろう。おそらくそこでデモ隊は団子状になり、勢いあまって「人民電車を出せ」と要求したのであろう。 “編集長が行く《吹田事件の現場を訪ねる 02》文・写真 Lapiz編集長 井上脩身” の続きを読む